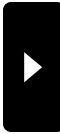2011年06月06日
修行3
カンナの刃、穂の表の刃先をカナズチのふといやつ、いわゆるゲンノウの角でこんこん叩くと、もちろん鉄道の線路をきってできた鉄台の角に当ててだけど、裏側すなわち鋼がふくれてくる、
それをカナ板の上に金粉を乗せ、カンナの裏を下にしてその上から木を当ててまっすぐこするするとうらがぴかぴかになる、それを、砥石で研ぐと穂先が真っ直ぐになる、叩きすぎると割れるし、これを丁寧にやると仕事がはやく、削り面がきれいになる。
弟子入りして直ぐやる事は、掃除はもちろんだけど木と木を貼り合わせる糊っくり、先ず米飯を両取っての付いたヘラで両脛を地面につけ糊台の、上でひたすら潰しトロリとするまでねる、そこで虫除けのための水に溶かしたリユウサン銅をまぜまたひたすら練り水分の調節をする、
ごはんが、ホチメシのときはたいへん良い糊ができない、夏は夏で腐って使えなくなる、また膝の下に、蛸、が出来なれる迄大変、この蛸ができることが修業の、一歩だと親方にどやされるこの頃は、間タンス(、タテよこ180センチ角-)和たんす(120//180~)が主でタンスの胴はモミの木、背な板は、モミか杉の木を貼りあわせて製作していた
それをカナ板の上に金粉を乗せ、カンナの裏を下にしてその上から木を当ててまっすぐこするするとうらがぴかぴかになる、それを、砥石で研ぐと穂先が真っ直ぐになる、叩きすぎると割れるし、これを丁寧にやると仕事がはやく、削り面がきれいになる。
弟子入りして直ぐやる事は、掃除はもちろんだけど木と木を貼り合わせる糊っくり、先ず米飯を両取っての付いたヘラで両脛を地面につけ糊台の、上でひたすら潰しトロリとするまでねる、そこで虫除けのための水に溶かしたリユウサン銅をまぜまたひたすら練り水分の調節をする、
ごはんが、ホチメシのときはたいへん良い糊ができない、夏は夏で腐って使えなくなる、また膝の下に、蛸、が出来なれる迄大変、この蛸ができることが修業の、一歩だと親方にどやされるこの頃は、間タンス(、タテよこ180センチ角-)和たんす(120//180~)が主でタンスの胴はモミの木、背な板は、モミか杉の木を貼りあわせて製作していた
Posted by カラス at 21:52│Comments(0)